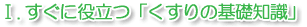 |
|
 |
1-1くすりの服用時間 |
|
|
|
| 薬には、それぞれ適した服用時間があります。食事の影響を受け易いもの、胃に障害を与え易いものがあり、それぞれ薬の性質によって正しい服用時間があります。 |
|
|
【食前:食事の30分前から60分前】
食物の影響を与え易い薬は、食欲増進剤、吐き気止め等は、食物が胃に入る前に服用します。
【食直後:食事のすぐ後】
胃に障害を与え易い薬は、食物で薬の刺激を和らげるために食物が胃の中にある時に服用します。
アスピリンは胃障害を起こし易いので食直後の服用が良い薬です。
【食後:食事をしてから30分以内】
多くの薬は一定時問ごとの服用のためにこの指示がされています。もし、飲み忘れるようでしたら、食事の後すぐ(食直後)に服用してもかまいません。
【食間:食事のおよそ2時間後に服用】
朝食と昼食の問のように、食事と次の食事の間に薬を飲むことです。
漢方薬は自然の薬草が原料ですから、吸収を良くする目的で、空腹時である食前または食間に服用します。また、生薬は苦味や特異臭があり、食物と一緒になると悪心が起きやすくなる場合もあり、食前または食問の服用が適します。
【寝る前:就寝およそ30分前に服用】
夜間の発作を予防する薬、排便を促す便秘薬や睡眠薬は医師の指示により就寝前に服用します。
【時間毎:食事に関係なく一定の間隔で】
体内で持続的効果を期待する薬は、食事に関係なく6時間毎、8時問毎、12時間毎等の服用が指示されます。生活のサイクルに併せて一定の間隔で服用してく
ださい。但し、安眠、休養も必要ですので多少の時間のズレは構いません。最近は一日朝一回の服用でよい徐放性製剤も開発されています。
【頓服:必要に応じて服用】
症状のひどい時に一時的に改善する薬ですので、必要に応じて飲みます。
配置薬では解熱剤、鎮痛剤、下剤、鎮咳剤が該当します。また、医療用では狭心症発作を止める薬、喘息発作を止める薬、検査薬、睡眠剤等があり、いずれも医師の指示を良く守って服用してください。すぐに効かないからと何回も飲むのは非常に危険です。
|
|
<<戻る |
|
|
 |
1-2くすりの飲み方も効果のうち |
|
|
|
|
【コップ一杯の水で飲みましょう】
飲む水の量が少ないと薬が食道にひっかかって、食道炎や潰瘍を作ったりすることがあります。
水も薬のうちであり、水は薬の吸収を良くします。
【体を起こして飲みましょう】
寝たままで飲むと、薬がのどや食道に長くとどまり、潰瘍の原因となります。
寝たままで飲むと、食道通過に時問がかかり、薬の効果が遅くなります。少なくとも90秒間は起きた状態でいてください。
寝たきりの老人や病人には、体を起こして薬を飲ませてあげましょう。
【水やぬるま湯(白湯)で飲みましょう】
抗生物質の中には牛乳で飲むと牛乳に含まれているカルシウムと結合して腸からの薬の吸収が悪くなり効き目が出にくくなるものもあります。
ジュースで飲んでいけない薬もあります。
鎮痛剤はお茶やコーヒーで飲むと吸収が良過ぎて副作用が出やすくなります。
鉄剤は鉄欠乏性貧血の人の鉄分を補給する薬です。以前はお茶で鉄剤を飲むとお茶のタンニンと鉄が結合して吸収されず効果がないと考えられていました。その後の研究ではお茶はそのような影響を与えないことが分かりました。鉄剤をお茶で飲んでも大丈夫です。
胃の悪い人は、水よりぬるま湯で飲むと良いでしょう。ぬるま湯は胃の温度を下げないので、胃の活動が妨害されず薬の吸収が良くなります。
いずれにしろ、薬は水または白湯で飲んでください。
|
|
<<戻る |
|
|
 |
1-3頓服薬の上手な服用方法 |
|
|
|
頓服薬は、一般的に発作時や症状のひどいときに一時的に飲む薬です。
頓服薬でも、例えば、かぜ薬や胃腸薬の容器または被包には、「一日3回食後服用してください」と表示されており、通常症状がおさまるまで数日問服用します。 |
|
|
【解熱鎮痛剤】
一般用では鎮痛作用と解熱作用がある解熱鎮痛薬が市販されています。
頭痛、歯痛、抜歯後の痩痛、月経痛、外傷痛の鎮痛等や悪寒・発熱時の解熱のある時に服用します。続けて服用する場合、なるべく空腹時をさけ一日2回服用の製品は6時間の間隔、一日3回服用の製品は4時問の問隔をおき服用します。
胃の痛みには解熱鎮痛薬ではなく、鎮痙薬を用います。
高熱の場合は解熱剤を服用すると同時に、氷枕や冷水で冷やすばかりでなく、薄着にしたり、掛け布団を薄くしたほうがよいでしょう。
【下剤】
通常便通が数日なく、さらに腹部の膨満感や吐き気などのある場合に用います。
寝る前に服用しますと、翌朝便通があるのが普通です。野菜、果物、水分のあるものなどを多めにとり、適度の運動をし、薬を用いないで済むように普段から心がけましょう。
【鎮咳剤】
から咳が強いときに服用します。通常一日4回以上の服用は避けてください。
この他、医療用医薬品(医師が使用するか、医師の処方せんや指示に基づき使用されることを目的とするもの)としては、以下のものがあります。
【狭心症発作止めの薬(舌下錠)】
狭心症の発作が起こったときに服用しますが、乱用は危険ですので医師の指示を守ってお飲みください。
舌下錠というのは、舌の下に錠剤を入れて服用するもので、薬が口腔内の粘膜から直接吸収されるため、通常1分以内に効果が現れます。噛み砕いたり、飲み込んだりしないように注意してください。最近では、発作予防に軟膏やテープ状の貼り薬も使われています。
【睡眠薬】
不眠症というのは、眠れないという苦痛で心身が緊張し、興奮するために起こることが多いのです。医師の指示に従い、1回量を厳守して服用しましょう。乱用してはいけません。また、薬の種類と量によっては翌朝眠気が残ることがあります。
アルコール類との併用は避けてください。
【喘息発作止めの薬】
乱用は危険ですので医師の指示を守って服用してください。内服薬のほかに坐剤や吸入薬もあります。
【検査薬】
検査前に決められた日時に服用します。病院から渡された用紙の指示どおりお飲みください。
|
|
<<戻る |
|
|
 |
1-4赤ちゃんの誤飲 |
|
|
赤ちゃんは目につくもの手にしたものを、何でも口の中に持っていきます。
そんなときに、すばやく.飲んだものを確かめることが大切です。病院へ行くときは、吐いたもの、飲み残したものを持っていきます。商品名がわかれば処揖の
仕方も適切に早くできます。日頃から薬品や口に入ってしまうような小さなものは、きちんと整理して赤ちゃんの手の届かない場所に保管しておきましょう。 |
|
|
【飲んでも、少量なら心配ないもの】
体温計の水銀(但し、ガラスの破片が□内に残っていたら、丁寧に取り除き医師のところへ。また、床などにこぼれた水銀の玉は気化するので有毒)、蚊取り線
香、蚊取りマット、マッチ、水彩絵の具(油絵の具は除く)、クレヨン、口紅、ベビーパウダー(但し吸い込んだときは、要注意)、タバコ(1/4本以上のと
きは吐かせる。また濡れている場合は、ニコチンが溶出し吸収されやすいので医師のところへ)。
これらは少量なら、□の中のものを取り出して清潔に拭き、赤ちゃんが普段と変わらない様子であれば心配ありません。
【これら以外のものを沢山飲んだときは、すぐ吐かせてください。】
水や牛乳を多めに飲ませて、赤ちゃんの顔を下にし、指先で喉の奥を刺激し、どんどん吐かせます。(但し、防虫剤、ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油、ペンキ、ラッカーなど脂肪に溶けやすいものは牛乳を飲ませてはいけません。)
【吐かせてはいけないもの】
酸やアルカリ(トイレ用剤、漂白剤等)が強いものは、吐かせると更に粘膜等が焼けただれます。牛乳を飲ませてからすぐに医師のところへつれていきます。
石油製品(灯油、シンナー、車の艶だし、家具の艶だし)も、吐かせず、この場合は牛乳は飲ませてはいけません。
痙攣やひきつけを起こしかけているとき、意識がもうろうとしているときも、吐かせてはいけません。
すぐ医師のところへ連れて行きましょう。
|
|
<<戻る |
|
|
| 1-5妊婦とくすり |
|
妊娠しておりますが、薬を服用してもかまいませんか?
妊娠中あるいは妊娠の可能性のある女性から、この薬を飲んでも大丈夫でしょうかという質問がしばしばあります。
母体に与えた薬が胎児に及ぼす影響一定ではありません。
妊娠時、体内では複雑な変化が起こってくるので、母体は機能低下をおこしやすく、薬の副作用も妊娠という特殊な状況のために、より強く発現することがあります。
このように薬は、直接あるいは二次的に胎児に影響するものですから、十分な注意が必要です。とくに妊娠初期から3,4ケ月の間は薬の服用、使用に気をつけなければならない時期です。
しかし妊娠期問中でも、たとえば糖尿病や心疾患など、それらを治療しておかなければ妊娠の継続が困難なときには、医師の指示のもとに、薬の服用が必要とさ
れる場合もあります。また、ビタミン剤、鉄剤、カルシウム剤や妊娠時に特異的に起こりやすい異常や疾患(たとえば、つわり、妊娠中毒症など)に対する治療
薬の服用も医師の指示を受けてください。
以上の理由から、妊娠中あるいは妊娠の可能性のある方は、診療科を問わず診察を受ける場合は、そのむねを主治医にお話し下さい。医師は細心の注意をはらって安全かつ有効と認められる薬を処方しますから、安心して服用、使用することができます。
|
|
<<戻る |
| 1-6抗生物質のはなし |
|
【抗生物質って何】
抗生物質とは、細菌を殺す薬です。体の中に入ってきたバイ菌が繁殖し、熱が出たりキズが化膿したりするのを抑える働きがあります。
【服用する際の注意】
1.白分の判断で中止しない!
症状が良くなったからといって、勝手に服薬を中止してはいけません。
薬の働きで細菌の繁殖が抑えられ、症状が良くなったように思えても、細菌を完全にやっつけてしまわないとまた、細菌が繁殖してしまいます。
2.血液中での薬の濃度を常に一・定以上に保つことによって、細菌を徹底的にやっつけます。そのためには、一定の間隔で薬を服用することが'人切です。
但し、1日3回服用の場合、8時間毎が適当ですが、安静を要する病人が夜中に起きてまで薬を服用する必要はありません。目安として、毎食後に忘れずにきちんと服用することが大切です。
3.抗生物質の中には、牛乳や胃薬(制酸剤)、鉄剤などと一緒に飲むと効呆が落ちるものがあります。分からないときは、医師や薬剤師によく聞いて、正しく服川してください。
4.妊婦や妊娠しているかもしれない婦人、授乳中の婦人は注意が必要なものがありますので、医師に申し出てください。
|
|
<<戻る |
| 1-7海外旅行に必要な携帯薬 |
|
国際化に伴いビジネスで、円高のメリットを海外旅行で享受と、毎年、海外へ旅行する方が増加しています。「旅行中に病気でせっかくの楽しい旅行がだいなし」とならないためにも簡単な携帯薬を持参しましょう。
【海外旅行中に病気になる主な原因】
1.時差、日程によるリズムの変化、2.環境に馴れないための緊張、興奮、3.食事の変化、4.団体旅行による人間関係のストレス、5.水や食事が原因で伝染病、食中毒
などでいろいろな病気にかかることが多いようです。海外旅行による一般的な症状に疲労、消化器症状(便秘、下痢)、不眠、食欲不振などがあげらます。
旅行中にこのような病気にかかってしまい、あわてて慣れない異国の薬局で薬を買うのも大変です。医者にかかるとますます面倒なことになります。高血圧等慢性疾患のある方は毎日飲んでいる薬を忘れずに、次の常備薬を携帯するのも安心です。
|
|
|
|
海外旅行時の携帯薬(一例) |
|
| 内服薬 |
整腸剤、健胃消化剤、総合感冒剤、解熱鎮痛剤薬、ビタミン剤、乗り物酔い薬、便秘薬 |
| 外用薬 |
消毒剤(マーキュロクローム、アルコール等)、目薬、虫刺され治療剤 |
| 衛生材料 |
救急バンソウコウ、包帯 |
|
|
|
|
なお、抗生物質、抗マラリア剤、睡眠導入薬などを携帯すべきときには、医師の指示が必要となります。
また、現在、医師の治療を受けて薬を飲んでいるかたは、相互作用に十分注意する必要がありますので、医師、薬剤師にあらかじめ相談してください。
一般的に、錠剤ならほとんどの税関を通りますが、粉薬は麻薬と勘違いされやすいのでなるべく控えるべきです。処方塞の写しなどを持っていくとよいでしょう。
【緊急事態発生】
病気になった場合:ホテルのフロントヘ連絡し、医師を呼んでもらう。また、日本大使館、領事館などで医師を紹介してくれる。費用は$50以上(アメリカ合
衆国)、日本と違って医療費は一般的に高額です。診察後、医師は処方塞を発行します。処方篭を薬局へ持っていき薬をもらいます。
|
|
<<戻る |
|
|